なぜ「階段昇降×グリコーゲン」が代謝改善に効くのか?
「しっかり運動しているのに、思ったより体が変わらない」
「階段の登り降りを続けているけど、本当に脂肪は燃えているのか不安…」
そんな疑問を感じたことはありませんか? 実は、階段の登り降りのような日常的な運動が「代謝を高める体」をつくるうえで非常に効果的であることが、近年の研究で明らかになっています。その中心的な役割を担うのが、筋肉内に蓄えられた “グリコーゲン” というエネルギー源です。
グリコーゲンは、筋肉を動かすためのガソリンのようなもの。これをどう使い、どう蓄えるかによって、「やせやすさ」や「疲れにくさ」、さらには「血糖コントロール」まで大きく変わってきます。
この記事では、グリコーゲンの基礎知識から、階段の登り降りがなぜ “グリコーゲン代謝を高める運動” として優れているのかを、科学的な根拠と実体験を交えながら解説します。特に40代以降の方にとって、無理なく続けられる “複利的な健康習慣” としてのヒントになれば幸いです。
だからこそ、今日から一段ずつ、始めてみませんか?
グリコーゲン代謝が促進されるとどうなる?:代謝が高い体の条件とは

「グリコーゲンをしっかり使える身体」は、すなわち「代謝が高く、疲れにくく、太りにくい身体」と言えます。ここで言う代謝とは、基礎代謝だけでなく、日々の活動におけるエネルギーの生産・利用・回復のサイクルがスムーズであることを意味します。
ではなぜ、グリコーゲン代謝の活性化がそれほど重要なのでしょうか?
筋肉の “回復力” と “出力” が上がる
グリコーゲンは筋肉の即効性エネルギー源であり、運動中に大量に使われます。激しい運動後に疲れが取れにくいと感じるのは、このグリコーゲンが十分に回復していないからかもしれません。
実際、ある研究では、筋肉内のグリコーゲン量が高い状態で運動すると持久力や筋出力が向上することが示されています。
日常的にグリコーゲン代謝を促す階段登り降りを行うことで、筋肉のエネルギー需要と回復のサイクルが整い、「疲れにくく、動ける体」へと近づけるのです。
代謝のスイッチが入りやすく、脂肪が燃えやすい体に
グリコーゲンが枯渇し始めると、体はその代替エネルギー源として脂肪を使い始めます。この代謝の切り替えスイッチがスムーズに働くことが、太りにくい体質への第一歩。
また、階段の登り降りのような高負荷トレーニングはEPOC(運動後過剰酸素消費)を引き起こし、運動後も数時間にわたって脂肪燃焼が続く状態を生み出します。
つまり、階段の登り降りでグリコーゲンを効率よく使える体に整えることは、運動時間外にも代謝を高める「燃焼体質」づくりにつながるのです。

インスリン感受性の向上で生活習慣病予防にも
筋肉内グリコーゲンは、インスリンの働きによって補充されます。筋肉でグリコーゲンがしっかり使われると、その補充の過程でインスリン感受性が高まります。これは、血糖値の安定や糖尿病予防にも直結する効果です。
特に40代以降は、加齢によりインスリン抵抗性が高まりやすくなるため、日常的に筋グリコーゲンを活用できる運動(=階段の登り降り)は、健康維持において極めて理にかなった習慣です。
空腹時やファスティングとの相性:脂肪燃焼との関係を解説

「運動するなら空腹時がいい」と聞いたことはありませんか?
これは一見危険にも思えますが、実はグリコーゲン代謝と脂肪燃焼の関係を知ると、その効果の理由が見えてきます。とりわけ、階段の登り降りのような中〜高強度の運動は、ファスティング中にも無理なく取り入れやすく、代謝改善に役立つのです。
空腹時運動が脂肪燃焼を促進する仕組み
空腹状態では、血糖が低下し、肝臓や筋肉に蓄えられたグリコーゲンがエネルギーとして使われ始めます。そして肝グリコーゲンが減ってくると、代わりに脂肪が分解されケトン体が生成される「代謝の切り替え」が始まります。
このスイッチが入ると、脂肪を効率的に燃やす “ケトン代謝モード” に突入。朝食前や夕食前の軽い階段の登り降りが、このスイッチを押す絶好のタイミングになります。
階段昇降は “糖質枯渇トレーニング” に近い
一部のアスリートが導入している「糖質を抑えた状態でのトレーニング(Low-glycogen training)」では、グリコーゲンが少ない状態で体を動かすことで、脂肪酸の利用効率やミトコンドリア機能が向上すると報告されています。
階段の登り降りはそれほど激しい運動ではないため、空腹時に行っても安全で、しかも筋グリコーゲンを適度に刺激することができます。これが脂肪のエネルギー化を促し、「太りにくく、疲れにくい」体質改善に寄与します。
ファスティングと併用すれば代謝効率はさらにアップ
私自身も実践している「12時間食間」のプチ断食と階段の登り降りを組み合わせれば、脂肪燃焼のタイミングをコントロールする生活が可能になります。
たとえば筆者の場合、最近は朝6時に朝食を摂り、6時45分前後から約50分間の階段登り降りを実践。その後は18〜19時まで食事を摂らず、“朝と夕の2食+日中断食” という生活リズムを保っています。
このスタイルなら、朝の運動までに朝食の糖がすでに消化吸収されており、階段の登り降りの運動負荷によって筋肉内グリコーゲンがしっかりと使われるタイミングになります。
一方で、前夜の夕食から朝食まで12時間空けることで、肝臓グリコーゲンの消費→脂肪燃焼スイッチへの切り替えも自然と促されます。
このように、運動と食事のタイミングを工夫することで、毎日 “無理なく脂肪が燃えやすい体内環境” を整えることが可能なのです。

出典:Glycogen availability and skeletal muscle adaptations with endurance and resistance exercise
継続することで得られる健康の “複利” 効果

金融の世界で「複利効果」といえば、利息が利息を生み、時間が経つほど資産が加速度的に増えていく現象を指します。実はこの “複利” の仕組みは、健康習慣にもそのまま当てはまるのです。
階段の登り降りを続けることで、筋肉内グリコーゲンの代謝効率は徐々に高まり、日常の中でのエネルギー循環がどんどんスムーズになっていきます。そしてこの小さな積み重ねこそが、数ヶ月後、数年後の体調や体型、さらには健康寿命に大きな差を生みます。
「筋肉の質」が変わると、代謝も変わる
継続的な運動で筋肉を刺激し続けると、筋繊維内のミトコンドリアの数や機能が改善されることが分かっています。ミトコンドリアは細胞内の “エネルギー工場” とも呼ばれ、脂肪酸やグリコーゲンをATP(エネルギー)に変換する役割を担っています。
このミトコンドリア機能が高まることで、
- 運動時のエネルギー効率が上がる
- 運動後の回復が早まる
- 脂肪酸の酸化能力が高まる
といった良循環が生まれ、「運動が楽になる→もっと動ける→また筋肉が活性化する」という健康のスパイラルが実現します。

グリコーゲン回復も “トレーニングされる”
一度運動でグリコーゲンをしっかり消費した後、体はそれをできるだけ早く回復しようとします。この「回復力」もまた、継続することで高まっていく能力のひとつです。
たとえば、
- 運動後の糖質摂取によるグリコーゲン再合成速度の向上
- インスリン感受性の改善
- グリコーゲン合成酵素の活性化
などが繰り返し刺激され、筋肉が “エネルギーを蓄えやすく、使いやすい” 状態に最適化されていきます。
これは単に「やせやすくなる」だけでなく、疲労しにくく、日常生活をアクティブに送れる身体作りにも直結する効果です。
習慣は未来への投資
一日一回の階段登り降りがたとえ数分でも、それが1ヶ月で30回、1年で365回、10年で3650回になります。
この回数分だけ、筋肉はグリコーゲンを使い、血糖は安定し、代謝は整っていきます。言い換えれば「小さな登り降りの習慣」が数年後の健康に“複利”で利いてくるというわけです。
40代から始めても決して遅くありません。だからこそ、今日から一段ずつ、一段ずつ、始めてみてください。

出典:Postexercise muscle glycogen resynthesis in humans
まとめ:今日から始める、代謝改善と体づくりの第一歩

階段の登り降りという何気ない動作の裏には、実は “代謝を高める科学的な仕組み” が隠されています。
特に今回注目した「筋肉内グリコーゲン」は、運動のパフォーマンスを支える燃料であると同時に、脂肪燃焼や疲労回復、血糖コントロールを左右する重要な存在でもあります。
グリコーゲンを意識した運動習慣 ―― たとえば、空腹時の軽い階段登り降りや、食後のグリコーゲン回復を助ける栄養補給 ―― を生活に取り入れることで、体は少しずつ「代謝が高く、太りにくく、疲れにくい」状態へと変化していきます。
そしてその変化は、一朝一夕ではありませんが、確実に積み重なっていく “健康の複利効果” として未来のあなたを支えてくれるでしょう。
だからこそ、今日から一段ずつ、始めてみませんか?
あなたの健康習慣づくりにも、階段の登り降りがきっと役立ちます。
おことわり
本記事は、筆者の実体験と医療従事者としての知見、ならびに信頼性の高い科学的文献をもとに執筆していますが、内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、すべての方に当てはまるとは限りません。
特に疾患をお持ちの方、服薬中の方、妊娠中・授乳中の方、また持病や健康状態に不安のある方は、運動・食事法・断食などの実践前に必ず医師や専門家にご相談ください。
記事内で紹介した研究結果やデータは、執筆時点のものであり、将来的に更新される可能性があります。あくまで参考情報としてご活用いただき、ご自身の健康判断は専門家の指導のもとで行っていただくようお願いいたします。
本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。





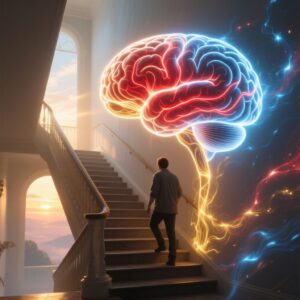





コメント