下肢を鍛え、空腹を味方にする:健康習慣の新しい形
階段の登り降りを健康習慣として続けていると、必ず気になってくるのが「エネルギーの使われ方」と「筋肉は減らないのか」という点です。私自身、この1年半ほどは中1〜2日で階段の登り降り朝活を行い、その後は10時間ほど食事までの時間を空けるというスタイルを続けてきました。
一方で、運動をしない日は12時間ごとに食事を摂るというリズムです。運動後に栄養を入れないことは筋肉に不利なのでは? という心配も正直あります。
しかし実際に続けてみると、体重コントロールや体調にはプラスが多く、思った以上に「健康維持」にちょうど良いバランスが見えてきました。今回はその体験と、科学的な背景を交えて解説していきます。
階段昇降と筋肉・グリコーゲンの関係

私たちの体は、“グリコーゲン” という形で炭水化物を貯蔵し、運動時にエネルギーとして活用しています。このグリコーゲンには、主に筋肉内に貯蔵されるものと、肝臓内にあるものの二種類があり、それぞれ役割が異なります。
筋肉内グリコーゲンは “その筋肉専用の燃料”
筋肉に蓄えられたグリコーゲンは、その筋肉自体の活動に使われる燃料であり、血液へ直接放出されることはありません。これは、筋肉に「グルコース‑6‑ホスファターゼ」がないためです(血糖として放出できない)。
したがって、階段の登り降りのような運動中は、使われるのはまさにその筋肉自身のグリコーゲンなのです。
出典:The Role of Skeletal Muscle Glycogen Breakdown for Regulation of Insulin Sensitivity by Exercise
肝臓のグリコーゲンは “血糖維持の要”
一方、肝臓にあるグリコーゲンは血糖値を維持するために使われます。運動によって血糖が下がってきたとき、肝臓は素早くグリコーゲンを分解して血糖へ変換し、脳や筋肉へのエネルギー供給を支えます。
特に運動が長時間かつ有酸素的な内容(階段の登り降りなど)では、肝臓グリコーゲンの役割は大きくなります。
出典:Glycogen
階段昇降は「中〜高強度の混合運動」
階段の登り降りは、持続的な動きでありながら、強度は高すぎない ― つまり有酸素運動と無酸素運動の中間に位置します。このため、筋肉グリコーゲンも有効に消費しつつ、同時に肝臓グリコーゲンも血糖維持のために使われるバランスの良い運動です。

運動後のグリコーゲン回復は “ゴールデンタイム” に進む
運動によって消費された筋肉グリコーゲンは、運動後すぐに摂取される炭水化物によって再合成されます。回復が最も進むのは運動後の最初の5〜6時間で、いわゆる “ゴールデンタイム” と呼ばれています。
このタイミングに栄養を補給することで、効率よく筋肉グリコーゲンの回復が進み、同時に疲労回復にもつながります。
補足:低グリコーゲン状態でのトレーニングの効果
興味深い研究では、「あえてグリコーゲンが少ない状態で運動する(Train‑Low)」ことで、筋細胞内の酸化的機能の向上や代謝シグナルが強化されるという報告もあります。
ただし、これはあくまで競技者レベルの「代謝適応を狙うトレーニング法」としての位置づけですので、健康維持を目的とする場合は、無理のない範囲で継続することが大切です。
出典:Glycogen availability and skeletal muscle adaptations with endurance and resistance exercise
小まとめ
階段の登り降りでは、主に筋肉グリコーゲンが使われる一方、肝臓グリコーゲンが血糖を維持する役割を担います。
運動後のグリコーゲン回復は最初の数時間がポイントであり、そこに栄養を投入できるかどうかが、リカバリーと代謝維持の鍵となります。
運動後に食事を空けると体内で何が起こるか

私が続けている階段の登り降り朝活のように50〜60分程度しっかり体を動かした後、通常であれば食事や間食で栄養を補給します。
しかしここで運動後10時間近く食事を摂らずに過ごすと、体の中ではどのような変化が起きるのでしょうか。
グリコーゲン再合成が進みにくい
運動によって消費された筋肉グリコーゲンは、通常であれば運動直後から再合成が始まります。特に最初の数時間は再合成速度が最も高く、摂取した炭水化物が効率よく筋肉に取り込まれます。
しかし、食事を取らないとこの「ゴールデンタイム」を逃してしまい、筋肉グリコーゲンの回復は遅れます。その結果、次の運動までの回復が不十分になりやすいのです。
肝臓グリコーゲンが血糖維持のために動員される
食事を取らない間も、体は脳や赤血球にグルコースを供給し続ける必要があります。そのため、肝臓グリコーゲンは血糖維持のために分解され、血中に放出されます。
運動である程度減った肝臓グリコーゲンがさらに消費されるため、10時間も空けるとかなり枯渇した状態になります。
出典:Glycogen
脂質利用が優位になる
肝臓グリコーゲンが減ってくると、体は代わりに脂肪酸を主な燃料として利用し始めます。筋肉は脂肪酸をエネルギー源に使うようになり、肝臓では脂肪酸からケトン体が産生され、脳にも供給されます。
これは「ファットアダプテーション(脂質利用能の強化)」とも呼ばれ、脂肪燃焼力を高める方向にはプラスです。
出典:Glycogen availability and skeletal muscle adaptations with endurance and resistance exercise
筋タンパク質の分解が進む
一方で、血糖を維持するための “糖新生” が活発になります。その材料として使われるのが、筋肉タンパク質由来のアミノ酸です。つまり、栄養が入らない時間が長いほど、筋肉の分解が少しずつ進むことになります。
1回の10時間断食で大きく筋肉が減るわけではありませんが、習慣化すると「合成<分解」となり、筋肉量はじわじわ低下しやすくなります。
出典:Skeletal Muscle Regulates Metabolism via Interorgan Crosstalk: Roles in Health and Disease
Fasting Hormones Synergistically Induce Amino Acid Catabolism Genes to Promote Gluconeogenesis
体感的な影響
- 疲労感の長引き:グリコーゲン回復が遅れるため。
- 集中力の低下:血糖が下がり気味になり、脳のパフォーマンスに影響。
- 脂肪燃焼の促進:一方で脂質利用が増えるので、ダイエット視点ではプラス。
小まとめ
運動後に長時間食事を取らないと、
- 筋肉グリコーゲンの回復が遅れる
- 肝臓グリコーゲンはさらに減る
- 脂質利用が優位になり、脂肪燃焼は進む
- ただし筋肉の分解リスクも増す
つまり、「脂肪燃焼には有利、筋肉維持には不利」という二面性を持つのです。
1年半続けて分かったメリットと課題

ここまで紹介してきたように、階段の登り降りと食事間隔を組み合わせる生活は、代謝や体組成に大きな影響を与えます。では実際に1年半ほど続けてみて、どのような手応えや課題が見えてきたのでしょうか。
やっていて良かった点
体調や体重の安定感
最も大きなメリットは「体調と体重が安定しやすい」という点です。階段の登り降りによる定期的な運動と、10〜12時間空ける食事リズムを組み合わせることで、体重の増減が緩やかになり、無理なくコントロールできるようになりました。血糖値の乱高下が少なく、消化のリズムも整いやすいと感じます。
これは、間欠的断食(Intermittent Fasting)が血糖コントロールや代謝に有利だとする研究報告とも一致しています。
出典:Effect of Time-Restricted Eating on Weight Loss in Adults With Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial
Time-Restricted Eating in Adults With Metabolic Syndrome
Intermittent fasting and health outcomes: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of randomised controlled trials
時間と習慣のメリハリ
「運動する日/食事まで10時間」「運動しない日/食事まで12時間」というパターンを決めているので、生活に自然とリズムが生まれます。
特に、運動をしない日は食事を12時間空けるというルールが、自分にとって “ブレーキ” の役割を果たしています。これは単なる食事制限というより、時間管理や生活習慣のフレームワーク(“枠組み” や “考え方の道具”)として働いているのです。
精神的な安心感
もう一つの大きな効果はメンタル面です。「自分は健康習慣をコントロールできている」という感覚が、継続によって強まりました。おかげで、食事や運動に過度に悩むことなく、習慣として淡々と続けられています。
こうした「自己効力感」は、健康行動の継続に大きな役割を果たすとされています。
ちょっと気になる点
筋肉の維持とのバランス
気になるのは、やはり筋肉量の維持です。特に12時間近く食事を空けた場合、筋肉分解のリスクがゼロではないため、高強度運動をした日には栄養補給とのバランスをどう取るかが課題として残ります。
柔軟性の少なさ
もう一つの課題は「柔軟性」です。生活パターンを固定している分、突発的な予定 ─ たとえば外食や残業、夜勤など─ が入った際に対応しにくくなるのです。ルールを守れないことが逆にストレスになる可能性も否定できません。
長期的な影響の不透明さ
最後に、長期的な影響についてはまだ不透明です。1年半の実感は良好ですが、5年、10年と続けた時に骨や関節、内分泌系にどう影響するのかは、現時点では分かりません。
特に加齢に伴って「空腹時間の長さ」が筋肉量やホルモン分泌にどう作用するかは、注意深く観察する必要があると感じています。
小まとめ
1年半の実践から見えてきたのは、「体調や体重の安定」「習慣のメリハリ」「精神的な安心感」といった大きなメリット。
一方で「筋肉維持」「柔軟性」「長期的影響」という課題もあります。言い換えれば、健康維持に有効な習慣でありつつ、今後も “調整” と “観察” が必要なライフスタイルだと言えます。
健康維持のための工夫:少量タンパク質の重要性

ここまで見てきたように、運動後に長時間食事を空けると、脂質代謝が高まる一方で、筋肉分解のリスクがじわじわと増していきます。
健康維持を目的とするなら、こうした “マイナス” をなるべく和らげる工夫が大切です。そのひとつが「運動後に少量のタンパク質を補給する」という方法です。
運動後は “分解と合成” の綱引き状態
運動をすると、筋肉の中では「分解」と「合成」が同時に起こります。運動刺激そのものは筋合成のスイッチを押しますが、その後に材料(アミノ酸)が入ってこないと、合成が進まず、分解が優位になってしまいます。
つまり、栄養が入るかどうかで、その後の体のバランスは大きく変わるのです。
牛乳200 mlのメリット
ここで便利なのが、牛乳のような手軽な食品です。200mlでおよそタンパク質6〜7 g、糖質9 g前後を含み、しかもホエイ+カゼインという2種類のタンパク質を持っています。
- ホエイ:吸収が速く、運動直後に素早くアミノ酸を届ける
- カゼイン:吸収がゆっくりで、その後の長時間の空腹をフォローする
さらに少量の糖質があることで、筋肉グリコーゲンの回復をわずかに後押しします。
現在の生活パターンとの相性
私の場合、朝6時に朝食を取り、その後は夕方まで水かブラックコーヒーで過ごしています。このスタイル自体が「時間制限食(Time-Restricted Feeding)」として、インスリン感受性の改善や体重管理に良い影響を与えることは多くの研究で報告されています。
ただし、階段の登り降りを行った日は筋肉への刺激が大きいため、朝食直後に運動をしても、その後10時間以上栄養が入らないのは「筋肉維持」という観点ではやや不利です。そこで、運動直後に牛乳コップ1杯を加えるだけで、筋肉分解リスクを大幅に下げられる可能性があります。

出典:Early Time-Restricted Feeding Improves Insulin Sensitivity, Blood Pressure, and Oxidative Stress Even without Weight Loss in Men with Prediabetes
Metabolic Effects of Intermittent Fasting
他の手軽な選択肢
もちろん牛乳にこだわる必要はありません。ヨーグルト100 g(タンパク質4 g)、ゆで卵1個(6 g)、無調整豆乳200 ml(7 g)なども同じように有効です。プロテインパウダーを水やブラックコーヒーに溶かして飲むのも手軽な方法です。
重要なのは「がっつり食事」ではなく「ほんの少しのタンパク質」をプラスすること。これだけで、筋肉合成シグナルを活かしながら、長時間の絶食のメリット(脂質代謝や血糖安定)も同時に得ることができます。
小まとめ
健康維持を目的とした「階段の登り降り+12時間ごとの食事」においては、運動後に少量のタンパク質を補給する工夫が有効です。
特に牛乳200mlは、速効性と持続性を兼ね備えた理想的な “軽い栄養補給” となります。これは食事リズムを大きく崩さずに取り入れられるため、無理なく続けられる工夫のひとつと言えるでしょう。
まとめ:健康維持の中庸を選ぶ

階段の登り降りと食事間隔を組み合わせる生活は、筋肉の合成と分解、脂質の燃焼と血糖維持といった「相反する力」をバランスさせる実践です。筋肉を大きく増やすわけでもなく、極端に削って痩せるわけでもない。そのちょうど中間に位置する習慣だからこそ、健康を長く保つために適しているのだと思います。
運動後に牛乳など少量のタンパク質を補うことで、筋肉分解を抑えつつ、空腹時間のメリットも享受できます。極端な方法に走らなくても、こうした小さな工夫を積み重ねることで「体調の安定」「習慣のリズム」「精神的な安心感」を得られるのです。
結局のところ、健康習慣はシンプルでナチュラル、そしてライフロングに続けられるかどうかが本質です。
私は「下肢を制すものは人生を制す」という思いを込めて階段の登り降りを続けています。
読者のみなさんも、自分のペースで無理なく続けられる方法を見つけ、長く健康を育てていきましょう。
おことわり
本記事は、筆者自身の実践経験および一般的に知られている健康情報をもとにまとめたものです。
医学的な診断や治療の代替となるものではありません。
運動や食事法の効果には個人差があり、体調や生活環境によって合う・合わない場合があります。
体調に異変を感じた場合や、持病をお持ちの方は、必ず医師など専門家にご相談ください。
本記事で使用した画像はNapkin AIを利用しています。
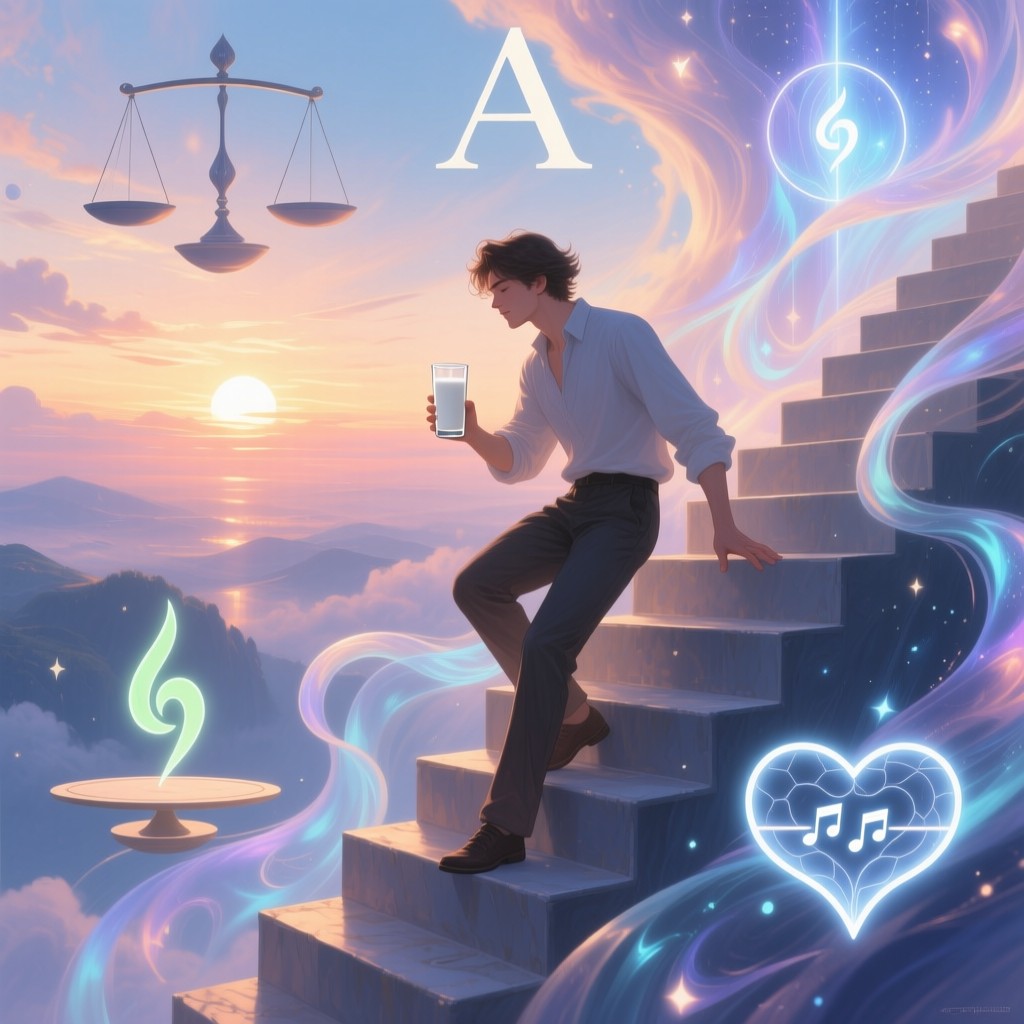







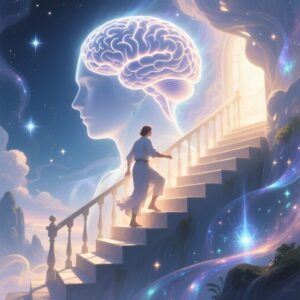


コメント